The Water is Wide
2014年04月12日
たまたま TVをみていたら久しぶりに聞きました。
決して 競艇のテーマソングではありません。
わりと有名なフォークソングです。
日本で一番有名なのはこの競艇のCMに使われた「カーラ・ボノフ」のヴァージョンでしょう。(間奏のアコーディオン ソロはThe Band の ガース・ハドソンです)
ギターを弾いているジェームス・テイラーも歌っています。
最後に、今はもう聞くことができない「Eva Cassidy」のThe Water is Wide
決して 競艇のテーマソングではありません。
わりと有名なフォークソングです。
日本で一番有名なのはこの競艇のCMに使われた「カーラ・ボノフ」のヴァージョンでしょう。(間奏のアコーディオン ソロはThe Band の ガース・ハドソンです)
ギターを弾いているジェームス・テイラーも歌っています。
最後に、今はもう聞くことができない「Eva Cassidy」のThe Water is Wide
Posted by 安儀製餡所 at 21:37
Down South in Osaka
│コメント(0)
理化学研究所と製餡業界
2014年04月10日
現在、世間の話題を独占している理化学研究所ですが、いまのところ得をしているのは非難が向かなくなった『佐村河内』氏だけという感じです。
さて、日本の最高峰の研究機関である「理化学研究所」と斜陽産業である製餡業界が直接関係がある筈がないのですが、過去にそこから派生した会社「理研ビタミン」と非常に緊迫した関係になったことがあります。
今から何年前だったか忘れましたが、何を思ったのか理研ビタミンが中国で加糖餡を製造し、日本市場で販売していました。
資本力、技術力は私たち「あんこ屋」では、到底太刀打ちできません。その上人件費が安く、規制の緩い中国で製造され、私たちが想像できないくらいの安価な加糖餡が市場に出回りました。
弊社のような零細企業の製餡所は日本から姿を消すのか?とも思いました。
が、結局、加糖餡を販売しても儲からないということで、さんざん市場を荒らして撤退しました。
さて、日本の最高峰の研究機関である「理化学研究所」と斜陽産業である製餡業界が直接関係がある筈がないのですが、過去にそこから派生した会社「理研ビタミン」と非常に緊迫した関係になったことがあります。
今から何年前だったか忘れましたが、何を思ったのか理研ビタミンが中国で加糖餡を製造し、日本市場で販売していました。
資本力、技術力は私たち「あんこ屋」では、到底太刀打ちできません。その上人件費が安く、規制の緩い中国で製造され、私たちが想像できないくらいの安価な加糖餡が市場に出回りました。
弊社のような零細企業の製餡所は日本から姿を消すのか?とも思いました。
が、結局、加糖餡を販売しても儲からないということで、さんざん市場を荒らして撤退しました。
夜の梅
2014年02月19日
産経新聞に連載されている永井 良和氏のコラム「関西街角文化論」で羊かんの「夜の梅」が紹介されていました。
「夜の梅」づくりの一端に関わる者として嬉しくなってくる文章なので、無断で申し訳ないのですが、ここでその一部を引用させてもらいたいと思います。
最後に 「夜の梅」の写真を載せたいところですが、この電光をあびていない夜の梅の写真というのが残念ながらなかなかありません。
そこで私が一番夜の梅のイメージに近いと勝手に思っているのが、スティーリー·ダンのアルバム『彩(エイジャ)』(Aja)のジャケットです。
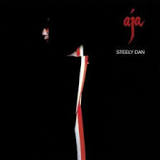
永井 良和氏は橋爪 紳也氏と「南海ホークスがあったころ」という本を執筆されています。年代的には私と同じで、南海ホークスのファンでその黄金時代を知らずに球団消滅の憂き目にあいました。
昨年堺市で開催された「南海ホークス 市民の暮らしとスポーツ」でも活躍されていました。

このポスターの真ん中に載っているのは、 かっての南海ホークスの大エース 杉浦 投手のアンダースローの美しい投球フォームです。
昨年の 楽天 田中 投手 の大活躍でそれに伴って少しは話題に登ることがあった昭和34年の杉浦投手の超人的な大活躍です。
「たしかに田中投手も素晴らしかったが、なんといっても杉浦投手の38勝4敗、日本シリーズ 4連投4連勝にはかなわない」
こんなことを飲み屋で話しているのは、100%南海ホークスのファンだった人と言えるでしょう。
「夜の梅」づくりの一端に関わる者として嬉しくなってくる文章なので、無断で申し訳ないのですが、ここでその一部を引用させてもらいたいと思います。
さまざまに工夫され種類が豊富な羊かんのなかでも、「夜の梅」は味わいのよさで知られる。命名の由来を想像できるだろうか。切り口に丸い小豆粒の断面がいくつか見え、それが闇夜に咲く梅花を思わせるところからだという。
以前、この連載で京都の「みなづき」をとりあげ、菓子が氷に見立てられることを書いた。同じように「夜の梅」も、初春の経験にかたちをあたえたかしである。
小豆と砂糖、そして寒天だけからつくられる菓子。素材の黒さを夜に、わずかに色の異なる小豆を花に。微妙な色あいの差を区別できる感度。闇夜を知る先人たちは、それをもっていた。
伏見と和歌山の駿河屋。京で創業し、明治維新で東京にも進出いた老舗・虎屋。大阪で親しまれる鶴屋八幡。つくり手はちがっても、「夜の梅」は関西でなじみ深い菓子だ。電光をあびない夜の花をめでる習慣も、たもっておきたい。
最後に 「夜の梅」の写真を載せたいところですが、この電光をあびていない夜の梅の写真というのが残念ながらなかなかありません。
そこで私が一番夜の梅のイメージに近いと勝手に思っているのが、スティーリー·ダンのアルバム『彩(エイジャ)』(Aja)のジャケットです。
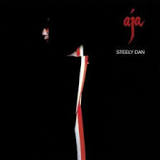
永井 良和氏は橋爪 紳也氏と「南海ホークスがあったころ」という本を執筆されています。年代的には私と同じで、南海ホークスのファンでその黄金時代を知らずに球団消滅の憂き目にあいました。
昨年堺市で開催された「南海ホークス 市民の暮らしとスポーツ」でも活躍されていました。

このポスターの真ん中に載っているのは、 かっての南海ホークスの大エース 杉浦 投手のアンダースローの美しい投球フォームです。
昨年の 楽天 田中 投手 の大活躍でそれに伴って少しは話題に登ることがあった昭和34年の杉浦投手の超人的な大活躍です。
「たしかに田中投手も素晴らしかったが、なんといっても杉浦投手の38勝4敗、日本シリーズ 4連投4連勝にはかなわない」
こんなことを飲み屋で話しているのは、100%南海ホークスのファンだった人と言えるでしょう。
ジクロロフェノールによる異臭騒ぎ
2014年01月09日
冷凍食品に次いで和菓子でも農薬によるとマスコミに報道されている異臭騒ぎ事件が起こっています。
報道では北米産のインゲン豆の残留農薬(ジクロロフェノール)が原因となっていますが、はたして他の可能性はないのでしょうか?
今回はジクロロフェノールによる異臭騒ぎの過去の事例を紹介したいと思います。
 甘納豆による苦情事例
甘納豆による苦情事例
 苦情内容
苦情内容
平成15年2月、都内で販売されている甘納豆について、「いつもの製品と味が違う」、「カルキ臭、消毒臭がする」などの苦情が保険所に寄せられた。
 検査結果
検査結果
検体からジクロロフェノールが検出された。
 混入原因
混入原因
配管修理に用いられたシール剤及び補修用塗料を塗布した鋼管の乾燥、沈管が不十分であったため、フェノール類が配管内に溶け出し、これがボイラー水として使用されていた水道水中の残留塩素と高温化で反応してクロロフェノール類(ジクロロフェノール)が生成したものと推察された。
そして、このクロロフェノール類を含む蒸気が釜の底部の亀裂から釜中に侵入し、製品の甘納豆を汚染したものと考えられる。
クロロフェノール類は官能関値がフェノールの1000分の1と低く、今回の事例のように0.001μg/g未満の非常に低い濃度においてもカルキ臭の原因となることが分かった。
今回でも原材料だけではなく製造工程にも可能性があるとは考えられないでしょうか。
それと農薬の残留検査を行ってもジクロロフェノールが検出されることは、まずありません。
なぜならばジクロロフェノールは農薬の材料として使われますが、これ単体で農薬として使用されることはないからです。
報道では北米産のインゲン豆の残留農薬(ジクロロフェノール)が原因となっていますが、はたして他の可能性はないのでしょうか?
今回はジクロロフェノールによる異臭騒ぎの過去の事例を紹介したいと思います。
 甘納豆による苦情事例
甘納豆による苦情事例 苦情内容
苦情内容平成15年2月、都内で販売されている甘納豆について、「いつもの製品と味が違う」、「カルキ臭、消毒臭がする」などの苦情が保険所に寄せられた。
 検査結果
検査結果検体からジクロロフェノールが検出された。
 混入原因
混入原因配管修理に用いられたシール剤及び補修用塗料を塗布した鋼管の乾燥、沈管が不十分であったため、フェノール類が配管内に溶け出し、これがボイラー水として使用されていた水道水中の残留塩素と高温化で反応してクロロフェノール類(ジクロロフェノール)が生成したものと推察された。
そして、このクロロフェノール類を含む蒸気が釜の底部の亀裂から釜中に侵入し、製品の甘納豆を汚染したものと考えられる。
クロロフェノール類は官能関値がフェノールの1000分の1と低く、今回の事例のように0.001μg/g未満の非常に低い濃度においてもカルキ臭の原因となることが分かった。
今回でも原材料だけではなく製造工程にも可能性があるとは考えられないでしょうか。
それと農薬の残留検査を行ってもジクロロフェノールが検出されることは、まずありません。
なぜならばジクロロフェノールは農薬の材料として使われますが、これ単体で農薬として使用されることはないからです。
乗鞍高原の晩秋
2013年11月18日
 友人Y氏が写真を送ってくれましたので掲載します。
友人Y氏が写真を送ってくれましたので掲載します。場所は、乗鞍高原、標高1500M辺り、乗鞍岳の朝焼け(モルゲンロート) 周りは終わりかけの紅葉と朝霜だったとのことです。
なんでもY氏は、この写真を撮るために大阪府貝塚市から乗鞍高原まで夜中車を運転し、とんぼ返りして、そのまま朝からテニスをしていました。
とても還暦を迎えた人とは思えません。









Posted by 安儀製餡所 at 18:58
photo gallery
│コメント(0)
あんこ好き
2013年11月04日
BRUTUS(11月1日号)という雑誌に「あんこ好き」というタイトルで和菓子やあんこの特集が掲載されています。
私も生まれて初めてBRUTUSを読みました。
そういえば、福山雅治さんが「あんこ好き」らしいので、その影響でこのような雑誌で特集になったのでしょうか?
いずれにしても、普段ほとんど取り上げられることのない あんこ ですから、このようなことはありがたい限りです。
内容はほとんどが有名和菓子店の紹介なのですが、 「あんこボーイのABC」 の章は あんこや小豆のことをあまりご存知ない方には興味深いのではないかと思います。
私も生まれて初めてBRUTUSを読みました。
そういえば、福山雅治さんが「あんこ好き」らしいので、その影響でこのような雑誌で特集になったのでしょうか?
いずれにしても、普段ほとんど取り上げられることのない あんこ ですから、このようなことはありがたい限りです。
内容はほとんどが有名和菓子店の紹介なのですが、 「あんこボーイのABC」 の章は あんこや小豆のことをあまりご存知ない方には興味深いのではないかと思います。
今一番売れている和菓子
2013年09月20日
先日、MBS毎日放送のある番組で「今一番売れている和菓子は「倍返し饅頭」である。」というようなことを放送していました。
一見、何の変哲もない黒糖饅頭のようですが、これが「倍返し」という魔法の焼印が押されるだけで、飛ぶように売れていくのだそうです。
MBSはTBS系列ですから身びいきもあるでしょうが、まあ、うらやましい限りです。衰えたりとは言え、TVの影響力はまだまだあるものだなあと感心します。
ひょっとしたら、いまごろ中国で「倍返し饅頭」のコピー商品を増産しているかもしれません。
TVといえば、先日テレビ朝日の「TVタックル」で中国産食品を取り上げていました。
このなかでコメンテイターと称する人たちが、「中国産食品は危険なのに検査する検体数が少ない」とか言っていましたが、TVで指摘するのは筋違いではないでしょうか?
民放TVの目的である視聴率、その視聴率調査こそが統計学的手法に基づき、私のような素人から見れば少なすぎるような検体数で調査して、その数字に支配されています。
デジタル放送化された現在ならば、技術的に全数検査が可能なTVがサンプル調査しかしていないのに、到底現実的に不可能な輸入食品の全数検査など要求するのは、少し矛盾しているように思いますが、どうでしょうか?
一見、何の変哲もない黒糖饅頭のようですが、これが「倍返し」という魔法の焼印が押されるだけで、飛ぶように売れていくのだそうです。
MBSはTBS系列ですから身びいきもあるでしょうが、まあ、うらやましい限りです。衰えたりとは言え、TVの影響力はまだまだあるものだなあと感心します。
ひょっとしたら、いまごろ中国で「倍返し饅頭」のコピー商品を増産しているかもしれません。
TVといえば、先日テレビ朝日の「TVタックル」で中国産食品を取り上げていました。
このなかでコメンテイターと称する人たちが、「中国産食品は危険なのに検査する検体数が少ない」とか言っていましたが、TVで指摘するのは筋違いではないでしょうか?
民放TVの目的である視聴率、その視聴率調査こそが統計学的手法に基づき、私のような素人から見れば少なすぎるような検体数で調査して、その数字に支配されています。
デジタル放送化された現在ならば、技術的に全数検査が可能なTVがサンプル調査しかしていないのに、到底現実的に不可能な輸入食品の全数検査など要求するのは、少し矛盾しているように思いますが、どうでしょうか?
「危ない中国産を見破る方法」という週刊文春の記事 3
2013年09月15日
今回は前々回で少し説明した餡の表示方法について、この記事から考えてみたいと思います。
以上が週刊文春に記載されていた記事です。
表示法に関する記述は正しいと言えます。ただし、付け加えると現実的には、「砂糖を加えた餡」以外の餡が一般に流通することは、「乾燥餡」を除いてほとんどありません。
 生餡
生餡
「乾燥餡」を除く、「砂糖を加えた餡」以外の餡とは私たちが「生餡」と呼んでいるものです。
ご覧になったことのない人も多いと思いますので、「生餡」とは以下の写真のものです。

生餡、小豆
これは水分が60%前後もあり、品質の管理が非常に難しく、普通小売店で販売されることはまずありません。それだけ商品の鮮度を保つことは難しいものです。
これらは和菓子店で加工されるか、自社で加工されて加糖餡となります。
一方、「乾燥餡」は読んで字のごとく、乾燥しているので、商品は痛むことはまずなく、小売店やネットで購入できます。
これが、「乾燥餡」と「生餡」の大きな違いです。
いずれにしても、消費者が食べるのは、「生餡」や「乾燥餡」ではなく、「加糖餡」だけなのです。
 加糖餡の表示
加糖餡の表示
現在、加糖餡(生餡に砂糖を加熱しながら練った練り餡)は下の表にあるように材料の原産地表示の義務はありません。

㈳菓子・食品新素材技術センター監修「わかりやすいお菓子の表示」
たしかに、消費者に流通しない「生餡」に原産地表示が必要で、流通している「加糖餡」に表示義務がないというのも不思議です。
その理由については、私も心当たりがありますが、確証があるわけではないのでここでは書きません。
 特色のある原材料
特色のある原材料
とありますが、実際には「特色のある原材料」として小豆についてはこの下の表にあるように様々な表示がされています。
㈳菓子・食品新素材技術センター監修「わかりやすいお菓子の表示」

しかしながら小豆を「特色のある原材料」として表示するのは「諸刃の刃」になるという側面があります。
小豆は農産物ですので、年によっては、各品種、生産場所、選別工程(豆の大きさ)によって、出来、収穫量が異なります。また周知の通り相場制のものですから、価格は年度、時期によって大きく変動します。
加糖餡にしても、それ自体での売り上げはたかがしれていて99%は、和菓子、パンに加工されます。
ですから、不作等何らかの理由で、収穫量が落ち込んで価格が急騰したからと言って、和菓子、パンメーカーの了解なしに
餡の値上げや原材料の変更ができません。
「特色のある原材料」を表示することはこのように「自縄自縛」におちいり、経営を悪化させる可能性があります。
したがって、「国産小豆」という表示はリスク回避という側面もあるのです。
現行の表示法では、餡は加工食品であっても原産地表示を義務付けられている。だが不思議なことに、「砂糖を加えた餡」は表示対象外となるのである。
要するに、私たちが和菓子やアンパンで口にしている甘い餡は、中国産であっても判別不可能。ときおり親切に「国産」と表示してある商品があるので、そうしたものを選びたい。
以上が週刊文春に記載されていた記事です。
表示法に関する記述は正しいと言えます。ただし、付け加えると現実的には、「砂糖を加えた餡」以外の餡が一般に流通することは、「乾燥餡」を除いてほとんどありません。
 生餡
生餡「乾燥餡」を除く、「砂糖を加えた餡」以外の餡とは私たちが「生餡」と呼んでいるものです。
ご覧になったことのない人も多いと思いますので、「生餡」とは以下の写真のものです。

生餡、小豆
これは水分が60%前後もあり、品質の管理が非常に難しく、普通小売店で販売されることはまずありません。それだけ商品の鮮度を保つことは難しいものです。
これらは和菓子店で加工されるか、自社で加工されて加糖餡となります。
一方、「乾燥餡」は読んで字のごとく、乾燥しているので、商品は痛むことはまずなく、小売店やネットで購入できます。
これが、「乾燥餡」と「生餡」の大きな違いです。
いずれにしても、消費者が食べるのは、「生餡」や「乾燥餡」ではなく、「加糖餡」だけなのです。
 加糖餡の表示
加糖餡の表示現在、加糖餡(生餡に砂糖を加熱しながら練った練り餡)は下の表にあるように材料の原産地表示の義務はありません。

㈳菓子・食品新素材技術センター監修「わかりやすいお菓子の表示」
たしかに、消費者に流通しない「生餡」に原産地表示が必要で、流通している「加糖餡」に表示義務がないというのも不思議です。
その理由については、私も心当たりがありますが、確証があるわけではないのでここでは書きません。
 特色のある原材料
特色のある原材料ときおり親切に「国産」と表示してある商品があるので、そうしたものを選びたい。
とありますが、実際には「特色のある原材料」として小豆についてはこの下の表にあるように様々な表示がされています。
㈳菓子・食品新素材技術センター監修「わかりやすいお菓子の表示」

しかしながら小豆を「特色のある原材料」として表示するのは「諸刃の刃」になるという側面があります。
小豆は農産物ですので、年によっては、各品種、生産場所、選別工程(豆の大きさ)によって、出来、収穫量が異なります。また周知の通り相場制のものですから、価格は年度、時期によって大きく変動します。
加糖餡にしても、それ自体での売り上げはたかがしれていて99%は、和菓子、パンに加工されます。
ですから、不作等何らかの理由で、収穫量が落ち込んで価格が急騰したからと言って、和菓子、パンメーカーの了解なしに
餡の値上げや原材料の変更ができません。
「特色のある原材料」を表示することはこのように「自縄自縛」におちいり、経営を悪化させる可能性があります。
したがって、「国産小豆」という表示はリスク回避という側面もあるのです。
「危ない中国産を見破る方法」という週刊文春の記事 2
2013年09月12日
前回の続きです。
私がこの記事を読んで次に疑問に思ったのは下記の件です。
餡の原料となる小豆は15,522トン中国産輸入品。砂糖を加えて練った餡そのものも、全輸入量の約7割が中国産なのだ。(週刊文春 9月12日号より)
これを読んで、私の同業者たちも口を揃えて「中国産が全輸入量の7割なんておかしい?95%の間違いだろう。これが本当なら残りの3割はどこで造っているのか?」
と疑問に感じています。
そこでどこかに加糖餡の国別輸入実績の統計がないか調べてみたら次の資料が見つかりました。
これは株式会社 丸勝のホームページに掲載されていたものです。

これから判断するとやはり7割はおかしいとおもうのですが?
私がこの記事を読んで次に疑問に思ったのは下記の件です。
餡の原料となる小豆は15,522トン中国産輸入品。砂糖を加えて練った餡そのものも、全輸入量の約7割が中国産なのだ。(週刊文春 9月12日号より)
これを読んで、私の同業者たちも口を揃えて「中国産が全輸入量の7割なんておかしい?95%の間違いだろう。これが本当なら残りの3割はどこで造っているのか?」
と疑問に感じています。
そこでどこかに加糖餡の国別輸入実績の統計がないか調べてみたら次の資料が見つかりました。
これは株式会社 丸勝のホームページに掲載されていたものです。

これから判断するとやはり7割はおかしいとおもうのですが?
「危ない中国産を見破る方法」という週刊文春の記事
2013年09月11日
週刊文春 9月12日号に「危ない中国産を見破る方法」という特集記事が掲載されていました。
この一連のシリーズで今回は和菓子や餡についても取り上げられていたので、興味を持って読んでみました。
しかしながら読んでみるとあんこ屋の常識からは考えられないような内容がありましたので、少し指摘してみます。
中国では餡を作る際、小豆以外に東南アジアから『ビルマ豆』という小豆の代用品を使って製造しています。しかし、ビルマ豆には『シアン青酸配糖体』という物質が含まれており、摂取すると体内で青酸カリを生成するのです。ビルマ豆を国内で使用する場合は基準が設けられていますが、中国での検査実態は疑わしい。(食品評論家・小藪浩二郎氏)
以上が週刊文春に掲載されていた内容です。
あんこ屋の立場から言わせてもらいますと、『ビルマ豆』(私たちは「バター豆」と通常呼んでいますので以後は「バター豆」とします)を小豆の代用品に使うことはまずありません。
「バター豆」はインゲン豆属ライ豆種に分類され、白餡を造る原材料として、主にミャンマーから輸入されてきました。
したがって、赤餡を造る原材料である「小豆」の代用品として「バター豆」を使うことはまずありません。
ただし、価格的にみれば、日本で購入すれば「バター豆」は「中国産小豆」より安いことから考えて、この記事にあるように中国の生産者が増量してコストを下げるために何パーセントか混ぜて使用する可能性はあります。(ただし、中国国内での
「バター豆」と「中国産小豆」の価格について実体はわかりませんが)
仮にこの記事の内容が事実ならば、次の問題があります。
①食品表示
中国製の加糖餡の赤こしあんや粒あんの原材料には「小豆」とともに「バター豆」も併記されなければなりません。もし表示されていないのであれば、偽装表示となります。
②シアン残留
シアン化合物といっても土壌、水質汚染や農薬、化学肥料などの影響で発生するものでは、決してありません。
豆科植物には、動物・昆虫による食害や微生物よる加害への対抗手段として、種子に種々の有害物質を含むものがあることが知られています。
例えば、大豆、いんげんまめ等には、種々のたんぱく質分解酵素阻害物質やレクチンと総称される赤血球凝集作用物質が含まれています。
また、東南アジアや中南米で生産されている「ライマメ」という種の豆には、シアン化合物(青酸配糖体のファゼオルナチン。リナマリンとも呼ばれる。)を含んでいるものがあります。
シアン化合物は、豆類以外にも梅、杏仁(アンズの種)、キャッサバ等にも含まれている成分で、含有量が多いと、植物内に含まれている分解酵素や腸内細菌により分解されて青酸(シアン化水素:HCN)を遊離し、食中毒の原因となる可能性があります。
しかし、豆類の場合、調理・加工時に繰り返し水にさらすことにより完全に除去することが可能です。
このため、日本では、豆類と生あんに関しては、食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の中で、流通、用途、製造方法等が規制されており、これにより食品としての安全性が確保されています。
以上は「豆類協会」H.P.からの引用です。詳しくはこのホームページを参照下さい。
 結論
結論
したがって、この週刊文春の記事が真実であるならば、中国製加糖餡はそれを食べた人に健康被害を与えることになります。
行政機関(消費者庁か厚生労働省かは知りませんが)は、中国製加糖餡については、原材料にインゲン豆の表示がなくてもシアン化合物の残留の有無を検査する必要があります。
以上、あくまでもこの記事を信用すればですが!
この一連のシリーズで今回は和菓子や餡についても取り上げられていたので、興味を持って読んでみました。
しかしながら読んでみるとあんこ屋の常識からは考えられないような内容がありましたので、少し指摘してみます。
中国では餡を作る際、小豆以外に東南アジアから『ビルマ豆』という小豆の代用品を使って製造しています。しかし、ビルマ豆には『シアン青酸配糖体』という物質が含まれており、摂取すると体内で青酸カリを生成するのです。ビルマ豆を国内で使用する場合は基準が設けられていますが、中国での検査実態は疑わしい。(食品評論家・小藪浩二郎氏)
以上が週刊文春に掲載されていた内容です。
あんこ屋の立場から言わせてもらいますと、『ビルマ豆』(私たちは「バター豆」と通常呼んでいますので以後は「バター豆」とします)を小豆の代用品に使うことはまずありません。
「バター豆」はインゲン豆属ライ豆種に分類され、白餡を造る原材料として、主にミャンマーから輸入されてきました。
したがって、赤餡を造る原材料である「小豆」の代用品として「バター豆」を使うことはまずありません。
ただし、価格的にみれば、日本で購入すれば「バター豆」は「中国産小豆」より安いことから考えて、この記事にあるように中国の生産者が増量してコストを下げるために何パーセントか混ぜて使用する可能性はあります。(ただし、中国国内での
「バター豆」と「中国産小豆」の価格について実体はわかりませんが)
仮にこの記事の内容が事実ならば、次の問題があります。
①食品表示
中国製の加糖餡の赤こしあんや粒あんの原材料には「小豆」とともに「バター豆」も併記されなければなりません。もし表示されていないのであれば、偽装表示となります。
②シアン残留
シアン化合物といっても土壌、水質汚染や農薬、化学肥料などの影響で発生するものでは、決してありません。
豆科植物には、動物・昆虫による食害や微生物よる加害への対抗手段として、種子に種々の有害物質を含むものがあることが知られています。
例えば、大豆、いんげんまめ等には、種々のたんぱく質分解酵素阻害物質やレクチンと総称される赤血球凝集作用物質が含まれています。
また、東南アジアや中南米で生産されている「ライマメ」という種の豆には、シアン化合物(青酸配糖体のファゼオルナチン。リナマリンとも呼ばれる。)を含んでいるものがあります。
シアン化合物は、豆類以外にも梅、杏仁(アンズの種)、キャッサバ等にも含まれている成分で、含有量が多いと、植物内に含まれている分解酵素や腸内細菌により分解されて青酸(シアン化水素:HCN)を遊離し、食中毒の原因となる可能性があります。
しかし、豆類の場合、調理・加工時に繰り返し水にさらすことにより完全に除去することが可能です。
このため、日本では、豆類と生あんに関しては、食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の中で、流通、用途、製造方法等が規制されており、これにより食品としての安全性が確保されています。
以上は「豆類協会」H.P.からの引用です。詳しくはこのホームページを参照下さい。
 結論
結論したがって、この週刊文春の記事が真実であるならば、中国製加糖餡はそれを食べた人に健康被害を与えることになります。
行政機関(消費者庁か厚生労働省かは知りませんが)は、中国製加糖餡については、原材料にインゲン豆の表示がなくてもシアン化合物の残留の有無を検査する必要があります。
以上、あくまでもこの記事を信用すればですが!
君の友達
2013年08月22日
さて、前回は『一角獣と貴婦人』 という タペストリー について書いてみたのですが、私たちの年代で、タペストリーといえば、20世紀文化遺産の一つ(と私は勝手に思っています)である、キャロル・キング のアルバムです。
私の子供が課題図書かなんかで、重松清氏の「きみのともだち」を読んでいたので、このタイトルの由来やキャロル・キングやジェームス・テイラーについて話したのですが、案の定嫌がられました。
さて、小説の「きみのともだち」の方ですが、映画化されました。
この中で一番印象に残っているシーンは、主人公の二人の少女がそれぞれの事情から、クラス対抗の大縄跳び大会で縄を回す役となってしまい、練習します。はじめは嫌々だったのが、徐々にうちとけていき、やがて休憩することとなり公園にある和菓子屋さんでお饅頭を買って2人で食べるところです。
最近は、以前はどんな町にもあったこのようなお店はすっかり減ってしまいました。
小奇麗でもなく、「何処どこ産の材料を使って」とかいう能書きはいちいち書いていませんが、安くて子供にとって買いやすい店は少なくなりました。
なにか、残念に思い、印象に残っています。
私の子供が課題図書かなんかで、重松清氏の「きみのともだち」を読んでいたので、このタイトルの由来やキャロル・キングやジェームス・テイラーについて話したのですが、案の定嫌がられました。
さて、小説の「きみのともだち」の方ですが、映画化されました。
この中で一番印象に残っているシーンは、主人公の二人の少女がそれぞれの事情から、クラス対抗の大縄跳び大会で縄を回す役となってしまい、練習します。はじめは嫌々だったのが、徐々にうちとけていき、やがて休憩することとなり公園にある和菓子屋さんでお饅頭を買って2人で食べるところです。
最近は、以前はどんな町にもあったこのようなお店はすっかり減ってしまいました。
小奇麗でもなく、「何処どこ産の材料を使って」とかいう能書きはいちいち書いていませんが、安くて子供にとって買いやすい店は少なくなりました。
なにか、残念に思い、印象に残っています。
Posted by 安儀製餡所 at 18:51
Down South in Osaka
│コメント(0)
一角獣と貴婦人
2013年08月15日
今年は日本で クリュニー美術館(中世美術館)の至宝「一角獣と貴婦人」展が開催されており、幸いなことに大阪でも現在開かれています。
私ももう少し涼しくなってから観に行こうと思っています。

さて、私にとって 「THE LADY AND THE UNICORN」 といえば 思いだされるのが JOHN RENBOURN の同名のアルバムです。
このアルバムは たしかJOHNにとって 4枚目のソロアルバムだったと思います。
これを買った時(LP盤です)は、このアルバムジャケットに使われている、タペストリーがこんなにも有名な美術品であるとは全く知りませんでした。
このアルバムは前作の傑作「Sir John Alot and Merrie England 」と比べるとBLUESの香りが全くなく、自称エリザベス朝のビッグ・ビル・ブルージーン的な演奏が聴けずに今一だなという感じでした。
JOHN RENBOURN 自身もライヴでこのタイトル曲を演奏することはあまりないようです。
「Sir John Alot and Merrie England 」 とくにB面(当時はそう言いました)の演奏は今聞いても楽しめます。
」
私ももう少し涼しくなってから観に行こうと思っています。

さて、私にとって 「THE LADY AND THE UNICORN」 といえば 思いだされるのが JOHN RENBOURN の同名のアルバムです。
このアルバムは たしかJOHNにとって 4枚目のソロアルバムだったと思います。
これを買った時(LP盤です)は、このアルバムジャケットに使われている、タペストリーがこんなにも有名な美術品であるとは全く知りませんでした。
このアルバムは前作の傑作「Sir John Alot and Merrie England 」と比べるとBLUESの香りが全くなく、自称エリザベス朝のビッグ・ビル・ブルージーン的な演奏が聴けずに今一だなという感じでした。
JOHN RENBOURN 自身もライヴでこのタイトル曲を演奏することはあまりないようです。
「Sir John Alot and Merrie England 」 とくにB面(当時はそう言いました)の演奏は今聞いても楽しめます。
」
Posted by 安儀製餡所 at 22:11
Down South in Osaka
│コメント(0)
辻占煎餅
2013年08月13日
今年の夏は今までの人生で最もたくさん 「フォーチュン クッキー」 という言葉を聞かされています。
実はこの「フォーチューン クッキー」 の ルーツ は日本の『辻占煎餅』にあるというのは結構有名な話で、
以前に紹介した 『和菓子のアン』 に次のように載っていました。
これを契機に 「辻占煎餅」 にも注目があつまれば嬉しいのですが。
実はこの「フォーチューン クッキー」 の ルーツ は日本の『辻占煎餅』にあるというのは結構有名な話で、
以前に紹介した 『和菓子のアン』 に次のように載っていました。
『大正時代に日系人が「辻占」をもとに作ったにが「フォーチュン クッキー」だと言われている。』(辻占の行方より)
これを契機に 「辻占煎餅」 にも注目があつまれば嬉しいのですが。
2013年 十勝
2013年07月17日
2013年 北海道 十勝の畑の風景写真(6~7月)を掲載します。
とくに福勝金時は非常に珍しいものです。


ながいも




北ロマン (小豆の品種の一つ) 北ロマン


メークイン メークイン


手亡 手亡


福勝金時 福勝金時
この品種は,「大正金時」に「福白金時」を交配して育成された固定品種であり,育成地(北海道河西郡芽室町)における成熟期は早生,草丈は中,子実の大小が大きい品種である。「大正金時」と比較して,若莢の斑紋の色がないこと等で,「北海金時」と比較して,子実の形が楕円体であることで区別性が認められる。
とくに福勝金時は非常に珍しいものです。
ながいも
北ロマン (小豆の品種の一つ) 北ロマン
メークイン メークイン
手亡 手亡
福勝金時 福勝金時
この品種は,「大正金時」に「福白金時」を交配して育成された固定品種であり,育成地(北海道河西郡芽室町)における成熟期は早生,草丈は中,子実の大小が大きい品種である。「大正金時」と比較して,若莢の斑紋の色がないこと等で,「北海金時」と比較して,子実の形が楕円体であることで区別性が認められる。
Posted by 安儀製餡所 at 15:48
photo gallery
│コメント(0)
あんこに対する海外の反応
2013年06月07日
外国人があんこを苦手な理由について書かれていたブログをたまたま見つけたので紹介します。
これは、引用元:the-great-anko-controversy を訳した記事のようです。
まあ、あんこにもいろいろなレベルのものがありますので、一概には言えないと思いますが、私からすれば、突っ込みどころは満載ですが、
「所詮、西洋人には和菓子の繊細な味は理解できない」 と攘夷的な発想ではなく、参考意見として読めば面白いと思います。
これは、引用元:the-great-anko-controversy を訳した記事のようです。
あんこに対する大いなる論争
論争、これはあんこに対する論争です。
あんこ(あるいは餡)については日本に住んでいる西洋圏の人達の間でも意見が分かれています。
これは甘く煮た小豆で、アジアでは広く使われています。
強烈に嫌われていることがほとんどで、私のようにあんこが好きなのは少数派に分類されているでしょうか。
意見の相違は過剰な言葉に変えられ、未だ翻ったことはありませんがキリンラガーやあんこなどはいずれそうなるかもしれません。
私にはそうなるだろうという考えがあります。
ここに私に起きたことを紹介しましょう。
初めて訪れた外国人にとって日本は最初のうちは戸惑いを感じる場所です。
人々は親切ではありますが、自分の見知った行動をとることはなくストレートな答えを得ることはしばし困難です。
物事があまりに手に負えなくなった時、人は馴染みのあるもので心を慰めようとするものです。
それこそが私の知っている外国人の多くがドーナツや菓子を買いに行く理由な訳です。
ドーナツは故郷のものにそっくり…チョコレートやバニラクリームがかかってて…しかし、彼女達がそれを一口食べた時そこには甘い何かが入っていたのです。
これは彼女たちを気落ちさせ、最後の一撃となってしまいます。
哀れ、あんこは取り除かれてしまうのです。
あんこは何も悪くありません。チョコになろうとしたことなど一度もないのですから。
私は幸運でした。
私が始めて日本に来たのは7歳の頃で、あんこを別の何かに間違えるようなこともなく、大好物な物として覚えたのですから。
これはチョコレートの代用ではないけど、良い物です。
アジアの多くが私に賛同してくれるでしょう。
スーパーマーケットに行けば、缶に詰まった様々なあんこを見ることが出来ます。
あんこは小豆のペーストと砂糖を混ぜて作られます。
これは日本、韓国、中国で様々なお菓子に使われています。
この甘くした豆はアイスやカキ氷の上にトッピングされたりもします。
甘いスープにして焼いた餅を浮かべたデザートとしてもよく使われています。
あんこは健康に良いデザートと考えているかもしれませんが、甘くするためにどれほどの砂糖が使われているかも考えておく方がいいかも。
あんこを食べる方法は山ほどありますが、私が好きなのは大福餅で包んだ物でしょうか。
餅、まだ遭遇したことのない人のために説明するならそれは米から作られた滑らかなペーストの事です。
古くから、時には国外でも、餅は中を刳り貫いた切り株で木槌で突き崩すことで作られてきました。
餅を作るのには2人の人間が必要です。
1人がつき、もう1人がその間にすばやく手を入れて返すことで餅になっていきます。
危険なように聞こえるかもしれませんが、リズムに乗ればかなり楽しいものです。
私もやってみました。
最近ではほとんどの場合電動の餅つき機で作るか、お店で買ってきています。
新鮮な餅は素晴らしいものです。
しなやかで柔らかく歯ごたえがあって、日本人が言うには赤ちゃんの腿のようだとか。
(それとも赤ちゃんの脚を餅の様だと言っていたのか、ちょっと思い出せませんが)
それは指に確かな感触を与える歯ごたえを持った柔らかな枕のようです。
そして、新鮮な餅にはそれ自身にはほとんど味がありません。
大福餅はあんこをしなやかな米ペーストで包んだもので、その独特な甘さと歯ごたえは和菓子以外だ似たものは知りません。
大福餅にはあんこを完璧につぶしてペーストにしたものと、単純にマッシュして粒を残したものがあります。
私は粒を残した物の方が好きですね。
大福餅には中にイチゴを隠しいれたイチゴ大福というスペシャルバラエティな物もあります。
これも好きですね。
バナナ大福というのも聞いた事がありますが実際に見たことはありませんし、その考えには若干の危険性を感じてます。
友人のメグミが言うには「バナナとあんこは合わない」とか。
私は彼女の言うことを半ば信じています。
私は2カ月おきくらいにシアトルにある巨大なアジアンスーパーマーケット”Uwajima”や海岸沿いにあるセントラルマーケットに行ってアジアの食材を買い込んでいます。
その時は毎回おやつとして大福餅を買ってます。
両方のお店に日本の同じブランドの大福餅が売られています。
家に戻ってすぐ、私は慎重に大福餅を開封してゆっくりと食べ、一噛み毎にしっかりと味わってます。
もちろん私はチョコレートも大好きなのですが、個人的にはこれも全く別物として同じくらい好きなのです。
特に大福餅として食べるときは。
レシピを紹介できないのが残念…日本人がどういう風にこれを作っているのか知らないもので。
(最近こちらのサイトで学んだし、こちらにもありますが)
大福餅は私が作るコツを知らない物のうちの1つです。
住んでる場所でいい大福餅が手に入れられない場合、例えば近くにアジアンマーケットがないような場所に引っ越した場合、間違いなく自作に動く事になるでしょう。
しかし私にとって家一杯の大福餅は危険なことかも。
(私の太腿がそれこそお餅のように膨らんでいくことになりそう)
1ヶ月ごとに制限されているのが私にとっては最善でそれで十分なのかも。
でも、もしあなたが大福餅が売られているのを見かけたのなら、試してみることをお勧めします。
あんこは決してチョコレートのようではありませんが、それ自身は凄く美味しいですから。
私があんこを好きなのは凄くラッキーなことだと自分で思ってます。
たくさんの人がその機会を逃してるだけに。
追記。
大福餅を自分で作ろうとしてる人へ。
読者の人がレシピを紹介しているサイトを教えてくれました。
どうやら凄くシンプルに作れそうです。
↓この記事につけられたコメント
●セーン
美味しいよね!
私はアジア出身の海外留学生なんだけど、大福餅は凄く人気のあるお菓子だと思ってる!
記事をありがとう!
でも、私の出身であるシンガポールでみんながあんこをチョコやバニラと比較してるかどうかはわからないな。
あんこはあんこでチョコはチョコ、バニラはバニラだよ。
●バーバラ
大福餅最高だよね。
日本ミュージアムと日本庭園に行った時、そこのカフェで売ってたんだ。
緑茶餅とあんこ餅(これはあまり好きじゃなかった)、それとマンゴー餅。
次の週にはその事をブログで書いて、餅に関する事を探してたからこの記事を読めて良かったよ!
●ジセレ
ワオ、私にとって甘い豆は全然異質なものじゃないよ。
(私はドミニカ人なんだ)
”甘い豆のデザートスープ”と呼ばれるHabichuelas con Dulceは1年に1度(四旬節で)作るデザートとして凄く人気なんだ。
甘い豆のアイスクリームだって食べたことある。
これも凄く人気だよ。
●エミー
Daifuku mochi ga daisuki!
あんことお餅はどんな形状でも好きだな。
クレイジーな位美味しいよね。
それに外国人の多くがあんこについて想像していた味と違うと嫌悪しているというあなたの指摘にも同意する。
素晴らしい記事だったよ!
natukashi(ノスタルジック)な気分になっちゃった。
●エミリー
小豆アイスは私のお気に入りなんだけど、当然のことながら地元のTrader Joe's(アメリカのスーパーマーケットチェーン)には置かれてないフレーバーなんだよね。
最近試した小豆のワンタン(お汁粉のことか?)にはがっかりしたけど、小豆のアイスは本当に好きなんだ。
●h.ハート
あんこ大好き!
ウマウマウマ~!
ゴマ餅も食べてみたことあるけど、油で揚げないゴマ団子みたいだったな。
●カレン
私も好き。
写真を見てるだけで涎が出ちゃうよ。
糖分は控えようと思ってるんだけど、アジアンマーケットに行くと山ほど買っちゃうんだよね。
美味し。
●ローラ
あんこは本当に好きなんだよね!
なんか食べたくなってきちゃったよ。
イチゴ大福は聞いたことなかったけど、美味しそう!
●ヒルダ
ここのブログはよく読むけどコメントすることはほとんどなかった。
でもこの記事には笑っちゃったよ。
私は緑茶のマカロンにあんこを入れた物について他の人と議論をしたことがあって、彼女はそのアイディアを気に入らなかったみたいなんだ。
私はあんこが好きで、外国人はあんこに対して別の味を予想するというあなたの意見には同意する。
私はペルシャ人で、あんこは飲んだり食べたりしてきた慣れ親しんだ味なんだよね。
私が警告したにもかかわらず友人達がそれを食べて、大抵ネガティブなリアクションをするのにはいつも笑っちゃうよ。
●エリザベスB
おお~、あんこ。
私大好きだよ。
お茶会の時に出される主菓子(柔らかいケーキ)」って食べたことある?
もの凄く細かな細工がしてあって、恍惚となる位美味しいんだ。
何だか食べたくなってきちゃったよ。
●カーベイ
小豆ペーストの事をあんこと呼ぶのは知らなかったけど、私はあんこ好きだよ!
私はロンドン生まれのロンドン育ちだけど、両親はインド出身で、小豆のペーストを何かにつけるような事はした事がなかった。
初めて小豆ペーストに遭遇したのはjin duiの中に入ってるのだったな。
(周りにゴマがまぶされた歯ごたえのある団子で、中に白餡かあんこが入ってるんだ)
大体10年位前のロンドンのチャイナタウンでのことだったよ。
パン屋のショーウィンドウに並んでて、試してみようと思ったんだ。
他の友達はあまり気に入らなかったみたいだけど、私は中に入ってたあんこが大好きになったよ!
●Mrs.L
私が初めて餅と呼ばれる物に出会ったのは Trader Joe'sの冷凍菓子コーナーだったな。
アイスクリームだった。
日本人街で餅を買って、中に豆が入っている事にどれほど私が驚いたのか想像してみて欲しいな。
多分私は日本食品店に戻って、どういう物なのか注意を払って調べ、心を開いて試すべきなのかも。
●ダイアン
私は普通のアメリカ人女性だけどあんこは大好きだよ。
ペースト状になったのが好き(粒が残ってるのだって)で、どんな物でもいけるよ。
サンフランシスコの日本人街にあるあんこが入った“fish”サンドウィッチだって好きなんだ。(訳注:タイ焼きのこと)
●シンディ
私の妹が小さな赤ちゃんだった時はみんなに餅って呼ばれてたよ。
確かに彼女は見た目も感触も小さなお餅みたいだったな。
キュートでデリシャス。
家ではあんこをいろんな方法で食べてるよ。
餅に入れたり、焼き菓子に入れたり、アイスに乗っけてコンデンスミルクを掛けたり、新年のケーキの中に入れてフライにしたり。
外はカリカリで中は柔らかで甘いんだ。
あなたもあんこを好きなことを知れて嬉しいよ。
●クッキークランブ
はぁ…私も普通の白人女性で、私はあんこが苦手なんだよね。
あなたは私のあんこ初体験を完璧に説明してくれたよ。
何か別なものだと思ってたんだ。
(チョコレート?)
でも、納豆は好きだよ。
●オーグレイス
私はラッキーだったみたい。
大学生の頃ルームメイトだった日本人に教えてもらって、すぐに好きになったんだ!
ここロンドンでもあんこを使った色んな物が手に入るけど、Uwajimaが懐かしくてしょうがないよ!
ロンドンにも日本人地区やチャイナタウンはあるけど、Uwajimaと同じものはないんだ!
●ジョン
自分はカリフォルニア出身で日本で働いたことがあるんだ。
ほとんどの友人達はあんこを口に入れるなり吐き出してたな。
彼らにとっては残念なことに、自分はあんこを大好きになったけど。
●アノニマス
私の日本でのあんこ体験は大体同じだな。
見た目はチョコレートなんだけど味は…何だこれは???
でも、その味に嵌っていったよ。
特に回りに黄な粉がまぶしてあるのは味と歯ごたえのコントラストが圧倒的だった!
その後行った東南アジアで食べた小豆のアイスバーにはこの言葉を送ろう。
ココナッツと小豆はコズミック的美味さだった。
チョコを連想して食べたら全然違う味だった、というケースが多いようです。
もっとも、元々豆を多く食べる国にとっては敷居が低い様でもあります。
和食ブームは今も続いており、いずれあんこも広く受け入れらるようになるかもしれません。
あんこ系は単体で食べるよりもお茶や牛乳と併せて食べると美味しさがいっそう引き立つ気が。
ともあれ、今年も一年よろしくお願いします!
まあ、あんこにもいろいろなレベルのものがありますので、一概には言えないと思いますが、私からすれば、突っ込みどころは満載ですが、
「所詮、西洋人には和菓子の繊細な味は理解できない」 と攘夷的な発想ではなく、参考意見として読めば面白いと思います。
大腸菌群
2013年05月24日
3月28日 発行の 週刊文春 に あなたが食べている『中国猛毒食品』 という特集記事が掲載されていました。
このなかで普段あまり耳慣れない 大腸菌群 という言葉が使われていました。
この記事では『中国汚染食品最新リスト」には 大腸菌群 と書かれていたのに 見出しでは 大腸菌 と書かれています。
単純な疑問として 大腸菌群 = 大腸菌 なのでしょうか?
以下は私の聞きかじりの知識ですが、大腸菌群と大腸菌について書いてみたいと思います。
 大腸菌群と、大腸菌は同じか?
大腸菌群と、大腸菌は同じか?
大腸菌群とは病原性大腸菌の集団ではありません。
結論から言えば 「大腸菌群が陽性であっても大腸菌が陰性の場合がある、また、大腸菌群が陰性であっても大腸菌が陽性である可能性がある」 ということです。
 大腸菌
大腸菌
まず大腸菌とは、人や動物の大腸内に存在する菌で、大便の中に沢山います。
腸内細菌として、大便と一緒に大腸菌も排出されますので、もちろん、排便された大便の中にも、大腸菌は存在します。腸内細菌である善玉菌や、悪玉菌もそうです。
犬や猫などの動物も、外で大便をすれば大便が土と混ざるので、土壌から、大腸菌がみつかる事もあるかもしれません、
しかし大腸菌は、土の中や水、空気中などで、環境中に存在する事は、あまりありません。
 大腸菌群
大腸菌群
大腸菌群とは、大腸菌と同じような性質をもっていますが、純粋に大腸菌の事だけを言うのではありません。
自然界に広く存在する、大便経由ではない大腸菌に分類されていない、多くの菌類を含んだものを、まとめて大腸菌群といいます。
大腸菌群は、人や動物の大便系とは、直接に関係のない自然界にも広く存在していますので、衛生管理のための汚染指標として活用されています。
加熱しない生鮮食品から、少量の大腸菌群が検出されたり、また加熱済みの食品からの菌が検出された場合は加熱が不十分であった可能性や加熱後に2次汚染した場合などが考えられます。
もしも、飲食店で大腸菌群が陽性になってしまった場合、食品の汚染指標になったりします。
また同じ腸内細菌で、食中毒菌であるサルモネラ等の汚染指標にもなります。
もし検査で検出されたのが、腸内に存在する大腸菌なら人や動物の大便からの汚染が予想されるます。
しかし、腸内に存在しない細菌だと、さらに視野を広げて、汚染の原因となっている、大腸菌群を調べる必要があります。
 大腸菌の細菌分類学上の定義
大腸菌の細菌分類学上の定義
大腸菌とは、細菌分類学上の言葉で、特定の性質を持ち、国際命名規約に準拠した学名Escherichia coliを持つ菌を指します。
大腸菌(だいちょうきん, Escherichia coli)は、グラム陰性の桿菌で通性嫌気性菌に属し、環境中に存在するバクテリアの主要な種の一つである。この菌は腸内細菌でもあり、温血動物(鳥類、哺乳類)の消化管内、特に大腸に生息する。アルファベットで短縮表記でE. coliとすることがある。
 大腸菌群の衛生学上の定義
大腸菌群の衛生学上の定義
先に「大腸菌群とは、大腸菌と同じような性質をもっている」と書きましたが具体的には以下の点を指しています。
大腸菌群とは、細菌学用語ではなく、便宜上の衛生学用語なのです。大腸菌群とは、「乳糖を分解し、酸とガスを産生するグラム陰性の好気性または通性嫌気性の無芽胞桿菌」と定義される細菌の集まりを指し、細菌検査法のうえから括られる集団を言います。
自然界に存在する大腸菌群の多くは、細菌分類学上のクレブジエラ属菌(Klebsiella spp.)、サイトロバクター属菌(Citrobacter spp.)、エンテロバクター属菌(Enterobacter spp.)などの汚水細菌がほとんどで大腸菌はごく少数派です。
また、食品衛生法の規格基準に出てくる大腸菌群は、以下の検査法から規定される行政用語なのです。
言い換えると 大腸菌群が陽性であっても大腸菌が陰性の場合があると同時に、大腸菌群が陰性であっても大腸菌が陽性である可能性があるということです。
このなかで普段あまり耳慣れない 大腸菌群 という言葉が使われていました。
この記事では『中国汚染食品最新リスト」には 大腸菌群 と書かれていたのに 見出しでは 大腸菌 と書かれています。
単純な疑問として 大腸菌群 = 大腸菌 なのでしょうか?
以下は私の聞きかじりの知識ですが、大腸菌群と大腸菌について書いてみたいと思います。
 大腸菌群と、大腸菌は同じか?
大腸菌群と、大腸菌は同じか?大腸菌群とは病原性大腸菌の集団ではありません。
結論から言えば 「大腸菌群が陽性であっても大腸菌が陰性の場合がある、また、大腸菌群が陰性であっても大腸菌が陽性である可能性がある」 ということです。
 大腸菌
大腸菌まず大腸菌とは、人や動物の大腸内に存在する菌で、大便の中に沢山います。
腸内細菌として、大便と一緒に大腸菌も排出されますので、もちろん、排便された大便の中にも、大腸菌は存在します。腸内細菌である善玉菌や、悪玉菌もそうです。
犬や猫などの動物も、外で大便をすれば大便が土と混ざるので、土壌から、大腸菌がみつかる事もあるかもしれません、
しかし大腸菌は、土の中や水、空気中などで、環境中に存在する事は、あまりありません。
 大腸菌群
大腸菌群大腸菌群とは、大腸菌と同じような性質をもっていますが、純粋に大腸菌の事だけを言うのではありません。
自然界に広く存在する、大便経由ではない大腸菌に分類されていない、多くの菌類を含んだものを、まとめて大腸菌群といいます。
大腸菌群は、人や動物の大便系とは、直接に関係のない自然界にも広く存在していますので、衛生管理のための汚染指標として活用されています。
加熱しない生鮮食品から、少量の大腸菌群が検出されたり、また加熱済みの食品からの菌が検出された場合は加熱が不十分であった可能性や加熱後に2次汚染した場合などが考えられます。
もしも、飲食店で大腸菌群が陽性になってしまった場合、食品の汚染指標になったりします。
また同じ腸内細菌で、食中毒菌であるサルモネラ等の汚染指標にもなります。
もし検査で検出されたのが、腸内に存在する大腸菌なら人や動物の大便からの汚染が予想されるます。
しかし、腸内に存在しない細菌だと、さらに視野を広げて、汚染の原因となっている、大腸菌群を調べる必要があります。
 大腸菌の細菌分類学上の定義
大腸菌の細菌分類学上の定義大腸菌とは、細菌分類学上の言葉で、特定の性質を持ち、国際命名規約に準拠した学名Escherichia coliを持つ菌を指します。
大腸菌(だいちょうきん, Escherichia coli)は、グラム陰性の桿菌で通性嫌気性菌に属し、環境中に存在するバクテリアの主要な種の一つである。この菌は腸内細菌でもあり、温血動物(鳥類、哺乳類)の消化管内、特に大腸に生息する。アルファベットで短縮表記でE. coliとすることがある。
 大腸菌群の衛生学上の定義
大腸菌群の衛生学上の定義先に「大腸菌群とは、大腸菌と同じような性質をもっている」と書きましたが具体的には以下の点を指しています。
大腸菌群とは、細菌学用語ではなく、便宜上の衛生学用語なのです。大腸菌群とは、「乳糖を分解し、酸とガスを産生するグラム陰性の好気性または通性嫌気性の無芽胞桿菌」と定義される細菌の集まりを指し、細菌検査法のうえから括られる集団を言います。
自然界に存在する大腸菌群の多くは、細菌分類学上のクレブジエラ属菌(Klebsiella spp.)、サイトロバクター属菌(Citrobacter spp.)、エンテロバクター属菌(Enterobacter spp.)などの汚水細菌がほとんどで大腸菌はごく少数派です。
また、食品衛生法の規格基準に出てくる大腸菌群は、以下の検査法から規定される行政用語なのです。
その検査法から規定される内容は「EC培地において44.5℃で増殖し、ガスを産生する菌」を指します。
従って、44.5℃で増殖しないか、増殖してもガスを産生しない大腸菌(かなり存在します)は E.coli (大腸菌群)ではないのです。
言い換えると 大腸菌群が陽性であっても大腸菌が陰性の場合があると同時に、大腸菌群が陰性であっても大腸菌が陽性である可能性があるということです。
WILL THE CIRCLE BE UNBROKEN ?
2013年03月31日
さて、多忙を極めた3月も終わりをつげます。
恒例の Allman Brothers Band Beacon Run も終わっています。
今年はGregg の体調はどうだったのでしょうか?
昨年のように最終日は腰痛で欠場ということはなければいいのですが。
検索していると次のようなブログがありました。
http://canra.cocolog-nifty.com/akicanrany/2013/03/allman-brothers.html
これによるとコンサートの様子は予想通り、お客は私のような オッサン が殆どでその人たちが騒いでいるみたいです。
さて、BEACON RUNに先立つ2013年2月25日 Dan Toler (9月23日, 1948 年生まれ), が亡くなりました。
死因は ルー・ゲーリック病ということです。
.Dan Toler は Gregg の裏切りによるAllman Brothers Band 解散後、Dickey Betts が結成した Dickey Betts & Great Southern に参加。
その後、再結成された Allman Brothers Band に Dickey Betts とともに参加。 1979-1982 までに3枚のアルバムEnlightened Rogues (1979), Reach for the Sky (1980) and Brothers of the Road (1981).を残します。
時代の波に乗りきれずAllman Brothers Bandは解散。
しばらく消息を聞かなかったGreggですが、その後、映画「ブラック レイン」 のエンディング「I'll Be Holding On 」 で久しぶりにその声を聞かせた後、同時にGregg Allman Band を結成、Dan Tolerはギタリストとして 「 I'm No Angel 」1987 「 Just Before The Bullets Fly」 1988 に参加します。
この後 Allman Brothers Band は再々結成され、Dickey BettsがWarren Haynes を連れてきて.Dan Toler は不参加でした。
2000年頃、得意の内紛からDickey Bettsが脱退し再びDickey Betts & Great Southern を結成、これに参加します。
Duane Allman、Berry Oakley、Lamar Williams、Allen Woody についで亡くなったAllman Brothers Band のメンバー、元メンバーということになります。
日本では春は別れの季節ということになっています。
私にとっても3月は、身内に不幸がありましてこの曲を思い出しました。
これは昔少し流行語になった Gregg の 「レイド バック」ツアー でのライブのようです。
恒例の Allman Brothers Band Beacon Run も終わっています。
今年はGregg の体調はどうだったのでしょうか?
昨年のように最終日は腰痛で欠場ということはなければいいのですが。
検索していると次のようなブログがありました。
http://canra.cocolog-nifty.com/akicanrany/2013/03/allman-brothers.html
これによるとコンサートの様子は予想通り、お客は私のような オッサン が殆どでその人たちが騒いでいるみたいです。
さて、BEACON RUNに先立つ2013年2月25日 Dan Toler (9月23日, 1948 年生まれ), が亡くなりました。
死因は ルー・ゲーリック病ということです。
.Dan Toler は Gregg の裏切りによるAllman Brothers Band 解散後、Dickey Betts が結成した Dickey Betts & Great Southern に参加。
その後、再結成された Allman Brothers Band に Dickey Betts とともに参加。 1979-1982 までに3枚のアルバムEnlightened Rogues (1979), Reach for the Sky (1980) and Brothers of the Road (1981).を残します。
時代の波に乗りきれずAllman Brothers Bandは解散。
しばらく消息を聞かなかったGreggですが、その後、映画「ブラック レイン」 のエンディング「I'll Be Holding On 」 で久しぶりにその声を聞かせた後、同時にGregg Allman Band を結成、Dan Tolerはギタリストとして 「 I'm No Angel 」1987 「 Just Before The Bullets Fly」 1988 に参加します。
この後 Allman Brothers Band は再々結成され、Dickey BettsがWarren Haynes を連れてきて.Dan Toler は不参加でした。
2000年頃、得意の内紛からDickey Bettsが脱退し再びDickey Betts & Great Southern を結成、これに参加します。
Duane Allman、Berry Oakley、Lamar Williams、Allen Woody についで亡くなったAllman Brothers Band のメンバー、元メンバーということになります。
日本では春は別れの季節ということになっています。
私にとっても3月は、身内に不幸がありましてこの曲を思い出しました。
これは昔少し流行語になった Gregg の 「レイド バック」ツアー でのライブのようです。
Posted by 安儀製餡所 at 23:08
Down South in Osaka
│コメント(0)
うぐいす(餅)は何色か?
2013年01月30日

まだ梅の花には少し早いのですが、早春にはつきもの 鶯(うぐいす)餅 について少し書いてみたいと思います。
 一般的な鶯餅
一般的な鶯餅一般的に鶯餅(うぐいすもち)は、こし餡を求肥などで包み、丸く包んだものを楕円形にし、左右に引っ張りうぐいすの形にし、うぐいす粉(緑色に着色したきな粉)をまぶして仕上げることが多い。
したがって、花札にある緑色をした鳥(鶯?)の色に近い、早春を感じさせる和菓子が鶯餅です。
 鶯餅の由来
鶯餅の由来天正年間(1580年代)の頃、大和郡山(現在の奈良県大和郡山市)の郡山城の城主であった豊臣秀長が兄の豊臣秀吉を招いた茶会を開く際に「珍菓を造れ」と命じ、御用菓子司であった菊屋治兵衛が粒餡を餅で包み、きな粉をまぶした餅菓子を献上しました。
秀吉はその餅を大いに気に入り「以来この餅を鶯餅と名付けよ」と菓銘を下賜した。
一説には全国の鶯餅の原型とも言われています。(以下は菊屋HPより参照)
現代では非常に親しみやすく手軽に買える和菓子ですが、誕生当時はなかなか由緒ある和菓子だったようです。
 御城の口餅
御城の口餅時代を経てこの餅は「御城の口餅」と通称がつけられるようになりました。
これは菊屋がお城の大門を出て町人街の1軒目にあたることから、いつしか「御城の口餅」(お城の入り口で売っているお餅)と通称が付けられ今日に至りました。
現代ではもち粉から求肥を作り、うぐいす粉をまぶすのが一般的となっているが、本家菊屋では餅米から餅をついて作り、きな粉は青大豆を使用しているということです。
 鶯は何色か?あるいは花札の鳥はメジロなのか!
鶯は何色か?あるいは花札の鳥はメジロなのか! 鶯とメジロの混同
鶯とメジロの混同 鶯
鶯 メジロ
メジロ上の写真を見た限りでは花札の緑色の鳥はメジロのようです。(以下ウィキペディアより)
メジロは梅の花蜜に目がなく、早春には梅の花を求めて集まってくる。また比較的警戒心が緩く、姿を観察しやすい。
いっぽう、梅が咲く頃によく通る声でさえずりはじめる鶯は警戒心がとても強く、声は聞こえど姿は見せず、薮の中からめったに出てこない。
また鶯は主に虫や木の実などを食べ、花蜜を吸うことはめったにない。
両種ともに春を告げる鳥として親しまれていたこともあってか、時期的・場所的に重なる両種は古くから混同されがちであった。
古来絵画にある「梅に鶯」の主題を見ても、「梅にメジロ」を描いてしまっている日本画家も多い。
まあ、このことから、花札に書かれている「緑色の鳥」は、メジロだと言ってもよいでしょう。
それでは、鶯餅の色は間違いで、言い換えるとあれは 「メジロ餅」 とでもよぶべきものなのでしょうか?
 鶯色とは
鶯色とは鶯色というとメジロの体色のような鮮やかな色を連想する人も多いのですが、JIS慣用色名に定められている鶯色は茶と黒のまざったような緑色をしています。
この色を鶯茶(うぐいすちゃ)ともいう。実際の鶯の体色は茶褐色であり、JISの鶯色は、鶯の羽を忠実に取材した色です。
また江戸時代中期には茶色味がかった鶯茶が女性の普段着の色として大流行したため、当時「鶯色」といえばこちらの色を指します。
 鶯茶はこのような色である。
鶯茶はこのような色である。 
 現在一般にイメージされる鶯色はこのような色である。
現在一般にイメージされる鶯色はこのような色である。
 青大豆
青大豆ここで注目すべきは、青大豆です。
青大豆は、普通の大豆と比べて、極端に生産量は少なく、したがって値段も非常に高価です。(尤も最近は海外から代替品となる豆も輸入されているとも聞いていますが。)
泉州では 青大豆 と言えば、くるみあん の材料として有名です。が、一般的には鶯餅用のきな粉の材料として知られています。
さて青大豆を使ったきな粉ですが、けっして、メジロのような色になるわけではありません。
私も 青大豆を使用しているという 鶯餅をいくつか食してみましたが、色的には普通の大豆(黄大豆)を使ったものとさほど変わりません。
 青大豆で作ったきな粉が青くない理由
青大豆で作ったきな粉が青くない理由その理由は、青大豆と言っても、枝豆のように豆の中まで青色をしている訳ではないからです。
青大豆より一般的である黒大豆を考えてみてください。
黒大豆は表面(皮)は真っ黒ですが、中の色は灰色のような色です。
黒大豆と同様に青大豆も豆の表面(皮)は青いのですが、中の色は黄大豆とあまり変わりません。
よって、きな粉に加工した場合、あまり普通のきな粉と色は変わりません。
言い換えると、現在良く使われている鶯粉ほど鮮やかな色でない青大豆を使ったきな粉こそが鶯の色に近いと言えなくもありません。
以下は私の推論です。
最初は鶯餅は青大豆のきな粉を使い、本来の鶯に近い色になっていた。
しかし、世間では花札にある緑色の鳥(メジロ)は春の新緑を感じさせ、これを鶯と呼ぶようになってきた。
一方青大豆はあまりにも高価であり、無理をしてこれを使うより安価で世間が鶯に持っているイメージの色に近い、うぐいす粉(緑色に着色したきな粉)を使った鶯餅になった。
このようなところではないでしょうか?
 鶯あん
鶯あん最後に「鶯あん」について少し書いてみたいと思います。
私の知っている鶯あんは青えんどうを原料にしたあんで、つぶあんにして田舎饅頭にしたり、泉州ではこしあんにして村雨を作ったりします。
また、東北では青えんどうをもどして皮をむき、砂糖で甘く煮たものを「富貴豆」と呼び、これを使ったあんを富貴餡と呼びます。
一説によると、豆を蒸かすから「ふき豆」と呼ばれていたのを、縁起がよいから、と「富貴」という文字があてられるようになったのだそうです。
和菓子のアン
2012年12月31日
お正月用の本として買った一冊が、坂木 司 著「和菓子のアン」 です。
何年か前に書評で紹介されていたのを憶えていたのですが、今回文庫本になっていました。
大変読み易くて和菓子の(特に上生菓子)の勉強にもなります。
私などもこの小説に登場する上生菓子をすべて見たことや食べたことがあるわけではありません。
今年はお店で見かけたらぜひ買って食べてみたいと思います。
深夜枠で「孤独のグルメ」や「深夜食堂」みたいにドラマ化されれば嬉しいのですが。
何年か前に書評で紹介されていたのを憶えていたのですが、今回文庫本になっていました。
大変読み易くて和菓子の(特に上生菓子)の勉強にもなります。
私などもこの小説に登場する上生菓子をすべて見たことや食べたことがあるわけではありません。
今年はお店で見かけたらぜひ買って食べてみたいと思います。
深夜枠で「孤独のグルメ」や「深夜食堂」みたいにドラマ化されれば嬉しいのですが。
もみじ饅頭
2012年12月06日
あんこ屋のブログで紅葉の写真ばっかり掲載してもしょがないので、今回は もみじ饅頭の話を。
と言いましても、弊社が取引をしている和菓子屋さんには もみじ饅頭 を作っているお店はありませんので、私の聞きかじ
りの情報だけです。
 もみじ饅頭とは
もみじ饅頭とは
 起源
起源
 一般的には次のように言われています。
一般的には次のように言われています。
 伊藤博文の冗談が起源とする説について
伊藤博文の冗談が起源とする説について
まあ、今日では セクハラ で大騒ぎになったことでしょう。
 構造・製法
構造・製法
 餡の種類
餡の種類
 こしあん
こしあん
 つぶあん
つぶあん
 白あん・抹茶あん・栗あん
白あん・抹茶あん・栗あん
 チーズ
チーズ
 チョコレート
チョコレート
 クリーム
クリーム
 その他
その他
 皮むきあん
皮むきあん
私が知っている限り、もみじ饅頭の特徴と言えるのは、赤こしあんに皮むきあんを使っているお店が多いことです。
ただし、全てのお店というわけではなく普通の赤こしあんを使っているお店もあります。
 製造方法
製造方法
皮むきあんとは、小豆を最初に軽く茹でてその表皮をむきます。その後煮豆して、篩に通してあん粒子を整え水に晒し、脱水します。
したがって、以前に説明した 豆ペーストで作るあん とは対極にあると言えます。
 特徴
特徴
いわば、小豆にある、ある種の「えぐみ」を完全に取り去り、小豆色の薄い、あっさりとした味のあんを作ることが目的です。
一言でいえば、「小豆で作る赤こしあんと、いんげん豆で作る白こしあん の中間のようなあん」 です。
 用途
用途
主な用途としては、他の素材や香りを生かしたい場合、たとえば 酒饅、パイ饅、タルト あるいは 鹿の子(かのこ)で使われます。
次にあんの色を薄くしたい場合、小豆は高級なものほど、赤みが紫色に近く、安価なものほど黒色に近くなっていきます。
したがって、薄い色のあんを使いたい時に、皮むきあん を使います。
いずれにしても、皮むきあん を作るのは、手間が掛かるのとともに、歩留まりも悪く通常のこしあんと比べ高コストになります。したがって、それに見合うだけの メリット があるということでしょう。
と言いましても、弊社が取引をしている和菓子屋さんには もみじ饅頭 を作っているお店はありませんので、私の聞きかじ
りの情報だけです。
 もみじ饅頭とは
もみじ饅頭とは紅葉の名所として知られる日本三景・安芸の宮島の名物で、代表的な土産品である。
現在では広島市内でも多くの店舗で購入が可能で、広島みやげとして全国的な知名度がある。
 起源
起源 一般的には次のように言われています。
一般的には次のように言われています。もみじ饅頭を発案した人物は明治後期の厳島(宮島)の和菓子職人、高津常助とされている。
島内の名所・紅葉谷の旅館「岩惣」には、当時伊藤博文やヘレン・ケラーら国内外の要人が多く投宿していたが、この岩惣に和菓子を納入していた高津は、宿の仲居から「紅葉谷の名にふさわしい菓子が作れないか」と依頼され、試行錯誤の結果、1906年に「紅葉形焼饅頭」を完成させた。
 伊藤博文の冗談が起源とする説について
伊藤博文の冗談が起源とする説についてもみじ饅頭の起源には伊藤博文がかかわっていたという説があり、今日でも広く流布している。
内容は、「伊藤が岩惣の茶屋で休憩していた折、給仕した娘の手を見て『なんと可愛らしい、もみじのような手であろう。焼いて食うたらさぞ美味しかろ』と冗談を言ったのを岩惣の女将が聞きとめ、饅頭屋がこの話をヒントに考案した」というものである。
まあ、今日では セクハラ で大騒ぎになったことでしょう。
 構造・製法
構造・製法焼饅頭の一種である。
小麦粉・卵・砂糖・蜂蜜を原料とするカステラ状の生地で餡を包み、モミジの葉をかたどった型に入れて焼き上げる。
餡はこしあんが基本で、製法についてはどの製造元でもほぼ同一である。
 餡の種類
餡の種類 こしあん
こしあん もみじ饅頭が誕生した1906年当時からの、もみじ饅頭の基本とされる餡。
 つぶあん
つぶあん 昭和初期、若き日の「ヒゲの殿下」こと高松宮宣仁親王が厳島を訪問した際、所望したのがきっかけで誕生した。
 白あん・抹茶あん・栗あん
白あん・抹茶あん・栗あん第二次世界大戦後に考案された。最中や栗まんじゅうなど、各地の銘菓を参考にしたもの。
 チーズ
チーズ1980年代、もみじ饅頭のブームが到来した際に考案された、最初の変わり種あん。食べる際に電子レンジで1個10~20秒加熱(500W)すると、チーズがとろけておいしくなる。
 チョコレート
チョコレート チーズ入りとほぼ同時期に登場し、扱う店舗数もチーズ入りと同程度。これも、少し温めるとチョコレートがとろけておいしい。また、冷凍庫で冷やしても味わいがよい。
 クリーム
クリーム カスタードクリームが入っている。
 その他
その他 りんご(角切りしたもの)、餅、クリームチーズ、芋あん、竹炭パウダー入り(にしき堂の黒もみじ)など、現在も新商品の開発が続いている。
 皮むきあん
皮むきあん私が知っている限り、もみじ饅頭の特徴と言えるのは、赤こしあんに皮むきあんを使っているお店が多いことです。
ただし、全てのお店というわけではなく普通の赤こしあんを使っているお店もあります。
 製造方法
製造方法皮むきあんとは、小豆を最初に軽く茹でてその表皮をむきます。その後煮豆して、篩に通してあん粒子を整え水に晒し、脱水します。
したがって、以前に説明した 豆ペーストで作るあん とは対極にあると言えます。
 特徴
特徴いわば、小豆にある、ある種の「えぐみ」を完全に取り去り、小豆色の薄い、あっさりとした味のあんを作ることが目的です。
一言でいえば、「小豆で作る赤こしあんと、いんげん豆で作る白こしあん の中間のようなあん」 です。
 用途
用途主な用途としては、他の素材や香りを生かしたい場合、たとえば 酒饅、パイ饅、タルト あるいは 鹿の子(かのこ)で使われます。
次にあんの色を薄くしたい場合、小豆は高級なものほど、赤みが紫色に近く、安価なものほど黒色に近くなっていきます。
したがって、薄い色のあんを使いたい時に、皮むきあん を使います。
いずれにしても、皮むきあん を作るのは、手間が掛かるのとともに、歩留まりも悪く通常のこしあんと比べ高コストになります。したがって、それに見合うだけの メリット があるということでしょう。














